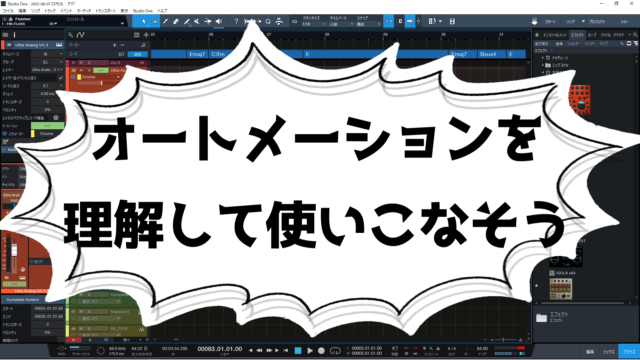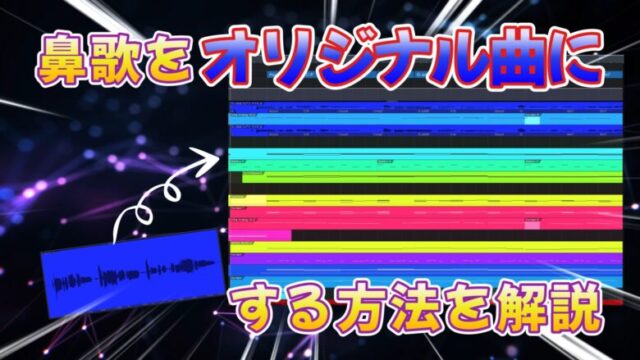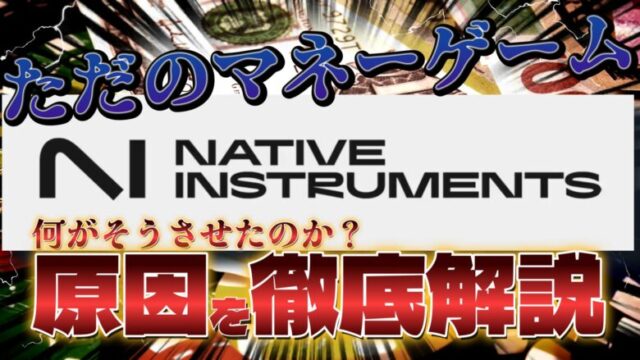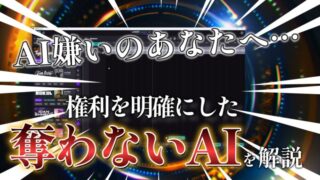【全部自腹推し記事】ミックスの悩みについて書かれたnote記事「現代mix考。」がとても有用だったので紹介!
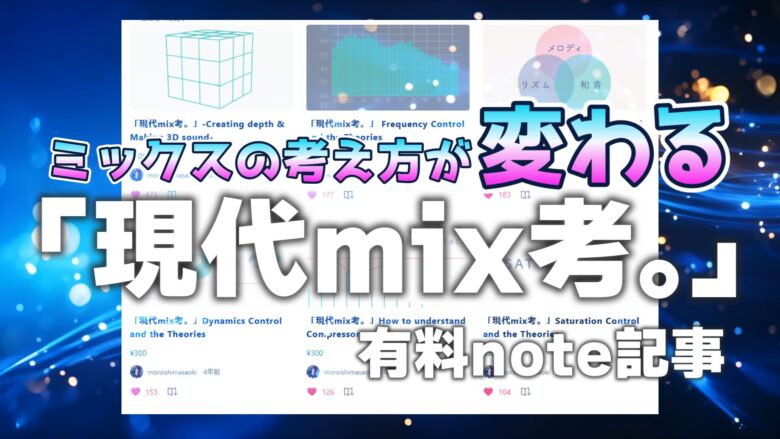


ミックスと言えば、DTM初心者の1番の悩みの種であり、例え中級者・上級者になってもそれを抜け出せない深い深い沼なのです。
かく言う私もその沼を抜け出せない一人なのですが、素敵なnote記事を見つけました。
有料記事ではありますが、読む価値がある良い記事だと思いましたので今回紹介させていただきます。
概要紹介
その前にひとつ…
この記事を私が書くにあたって、私は筆者から何も受け取っておらず、金銭的な利益が無いことを説明しておきます。
受け取ったものと言えば、自腹購入した記事の濃厚な中身と考え方ぐらいなものです。
至極単純に、「とても良い記事だな」「多くの人に知って貰いたいな」ぐらいの気持ちで書いていることをご了承ください。
筆者について
諸石政興さんというマスタリングエンジニアが執筆されています。
X上での活動報告もさることながら質問箱への回答もたくさんされていて回答の内容や真摯な回答の姿勢が非常に勉強になります。
noteシリーズについて
現在、7記事が公開・販売されています。
最終更新が1年前なので、続編を今か今かと待ちわびているのですが…。
シリーズ内容は以下の通りです。
Creating depth & Making 3D sound
前書きから始まり、現代的なミックスとは?立体的なミックスとは?と言った、基本的な筆者の考え方などが書かれている。
Frequency Control and the Theories
立体的なミックスは「周波数」「輪郭」「残響」の3つが重要であり、この章では「周波数」にまつわる情報を重点的に記載している。
How to understand EQ
2章で説明した「周波数」を扱う時に欠かせない「EQ」というエフェクターをどう捉えるか?そして、うまく扱うための考え方や実践的なコツを記載している。
Dynamics Control and the Theories
音の輪郭を作る、ダイナミクスとトランジェントについての回。後述する5章に繋がる内容でそもそも「ダイナミクス」とは?「近い音・遠い音」とは?について整理・言及している。
How to understand Compressor
コンプレッサーというエフェクターの動作原理といった基礎的な部分からパラレルコンプやサイドチェーンなどの実践的な内容を解説している。
Saturation Control and the Theories
ミックスのバリエーションを豊かにするために必要な「サチュレーション」とは何か?歪みだけでない重要な側面を説明しつつ、キャラクターごとの筆者おすすめの方法論を紹介している。
How to Treat Saturation?
サチュレーションの倍音とそれらが発揮するキャラクターや効果について言及しつつ、実践的なワークフローについて書かれている。
第1章無料記事分の紹介
まえがき
上記で述べた、全7章は各300円と有料記事ですが、無料で読める部分が章によってはそれなりに多く大事なことを書いていることが多いです。
前書きを読んでいくと、独学スタートで少しずつ努力を重ねて知見や技術を磨いて来られたことが分かります。
本文の中で、
当書籍では、アマチュアだからこそわからない視点、アマチュアではじめたからこそ気づけた視点を交えて、そして、マスタリングエンジニアだからこそ語れるミックスについて語っていきます。
本文より引用
とあるように、難しい言葉を使わずにかみ砕いて図解してくれていたり、実践的なワークを交えながらより理解が深まりやすいように記述してくれています。
オススメのプラグインや具体的すぎる使い方ばかりが載っていて、そもそもミックスがどういうものなのか語られているものは少ないように感じる。
(中略)
だからこそ、ここで僕が読者の皆さんにお伝えしたいのは、インターネットでサクッと調べれば出てくるTIPSのようなものではなくて、考え方、向き合い方だ。
(中略)
そうなってくると、本当に必要な情報は「有名エンジニアの〇〇はこのプラグインを使っています、この機材を使っています」という情報ではなくて、「〇〇さんはその道具をどういう風に捉えている」という情報こそが真に役立つ情報になってくるはずだ。本文より引用
まさに、情報が民主化されてプロアマ問わず発信ができるようになった今、その情報をどのように理解して自分の中に落とし込めるかの「取捨選択」が肝になっています。
かく言う私も、ミックスのTIPSを探してフンフンと理解したような気になっていますが、そのTIPSの裏に隠れた本質的なプロセスがごっそりと抜け落ちているような気がしてならず、その穴を埋めるためにまた別の「革新的なTIPS」を探す旅に出るという悪循環…。


そして、このシリーズに通底する「現代的なミックスとは?」「立体的なミックスとは?」を説明してくれています。
音をボールで考える
それぞれのパートをボールで考え、それを箱の中(2mix)に詰めていく。
音の遠近感を感じさせながら、立体的なミックスを作っていくために必要な工程や方法を書いた2~6章は全て最終的にこの考え方に帰結するように書かれています。
音同士の相対関係をイメージしながら配置をしていく、という大事なフレーズの後に記事は有料部分に入っていきます。


ここから先は、具体的なワークフローだったり、リファレンス曲の選びや使い方を解説してくれています。
気になる方は是非。
オススメできる点
ミックスに向かう姿勢が明確
具体的で局所的なTIPSというよりかは、「そもそもミックスが向かう終着点はどこなのか?」ということが書いてあり、すべてが第1章の「立体的な現代的ミックス」の作り方というところに帰結します。
何章にも渡り体系的に書かれているので、色んなTIPSで頭がこんがらがったりせず、ケースバイケースで応用の効く知識が蓄えられていきます。
EQの章では「相対関係のメリハリをつける時のみにEQは真価を発揮する」と書かれていて、よりクリーンで簡潔なミックスを目指すためにまずはフェーダーでバランスをとることを勧めています。
この文言は、ネット界隈でもたまに見かけますが、その根拠がちゃんと図示されていたりするため理解と納得がしやすいです。
私が読んでいて大事に思った一文を引用しておきます。
ここで強調をしておきたいのは、EQはフェーダーバランスの補足をするモノであって、フェーダーバランスの代わりになるわけではないということだ。
もしも、プロジェクト全体を見渡して、EQがトラックの6割以上にかかっているとしたら、それはフェーダーバランスを見直した方が仕上がりが良くなるはずだ。本文より引用
科学的な原理も説明してくれる
等ラウドネス曲線や位相についてや、二次倍音や三次倍音など、難しそうな現象やなんとなく知ってるけど…みたいな内容も言葉と図解を使って説明してくれているので、初心者の方も飲み込みやすいのではと思います。


具体的な数値や使い方を上げて、「はい!こんな仕上がりです!」で終わっているのではなく、なぜそう聴こえるのか、実生活からの実験、動作のメカニズムを丁寧に説明してくれています。
それらを知ることで、より柔軟で自分らしさのあるツールの使い方が出来るように一貫して書かれている点がおすすめできる点です。
何度も読み返したくなる
専門書のような難しい言葉もなく、ミックスの土台となる考え方が身に付く本シリーズ。
いわゆる虎の巻というか、代々継がれていくスタジオ内での秘儀みたいな核となる部分の内容が盛りだくさんに含まれていて、非常に勉強になります。
初心者の方は頭の片隅に置いておいて、ミックスの方向性を読み進めながら決めていくのがいいと思うし、中級者以上の方は、自分の今までの制作と向き合いより良いフローを構築するきっかけになります。
何度も書いたように「立体的な現代的ミックス」というゴールに向かってどのツールをどう捉えるかという話に終始しているので、分かりやすく、こんがらがってきたら第1章に戻ればいいという親切設計です。
ネット上では、やけに言葉が強かったり人の作品を貶めたりするのを見かけてしまいます。
自分の事ではないと思っていても胸がモヤモヤしてしまったり、いくら実績がある人でも「こんな言葉遣い、やだなぁ…」と引いてしまったりすることが私はあります。
そんな中、この筆者の文章からは、そういう尖った言葉遣いが見られず安心して読み進められるのも私が推す一つの理由なのかもしれません。
このブログ記事が、皆さんの音楽制作に役立つ情報を提供できることを願っています。
さらに詳しい情報や、ご意見ご感想があればぜひコメントをお待ちしています。